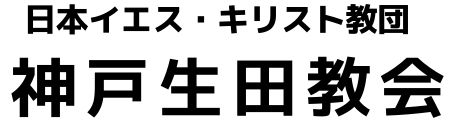礼拝説教「いつくしみの時、定めの時」2022年10月16日
聖書 詩篇102篇1~28節
(序)詩篇102篇は、苦しみの中から救いを叫び求めている祈りです。
- 苦しみ、嘆きを御前に注ぎ出して祈る
表題に「苦しむ者の祈り。彼が気落ちして、自分の嘆きを主の御前に注ぎ出したときのもの」とあります。本篇の詩人は、非常な苦しみの中から主に向かって叫び祈っています。詩人は、神が御顔を隠されたように感じるほどの非常に激しい苦しみを感じています。祈っても、叫んでも、答えがない。叫びが闇の中に吸い込まれるようで、何の応答もない。まさに沈黙の中に置かれています。
3節、詩人は、自分の存在が、煙の中に尽き果て、骨が炉の中にいるように熱く熱を帯び、いたたまれません。4節、心は、青菜のように打たれて、しおれ、パンを食べることさえ忘れた。すなわち、食欲も生きる気力も、何もかも失ってしまったのです。5節、ことばにならないうめきによって、骨が肉のうちに溶けるというのです。それは、荒野や廃墟で寂しく泣き声を上げるミミズクやフクロウのごとくだというのです。いつでしたか。NHKの番組で、メスのフクロウが泣く声が人の叫びのような声で気味が悪いと住民が証言している映像がありました。それはギャーと何とも言えない不気味な声でした。そのような叫びをあげている自分だ、と詩人は感じているのです。7節、眠ることも出来ない。ただ群れからはぐれて、一人孤独なはぐれ鳥のように、ヒク、ヒクと風前の灯火のような弱弱しい声を漏らしているというのです。
しかも、8~11節、詩人には、容赦なくそしりと、嘲りの声を浴びせられ、灰を噛むような、あるいは砂を噛むような状況に置かれ、涙をのませられているのです。
- いつくしみの時、定めの時に目を注ぐ
しかし、12節をご覧ください。「しかし、主よ。あなたはとこしえに御座に着いておられます。あなたの呼び名は代々に及びます」とあります。詩人は失望と落胆の泥沼に引き込まれるような中にあって、主を見上げたのです。主のあわれみと慈しみに目を向け、「いつくしみの時と定めの時」に、しっかりと目を留め、焦点を合わせたのです。詩人を取り巻く状況は依然として暗黒であっても、詩人は、今、もうそこに、「いつくしみの時と定めの時」を見ています。15~16節、国々は、そして地のすべての王たちは、主の御名と主の栄光を見て、恐れるというのです。詩人は、主の救いと栄光を見ているのです。そこにいます主の臨在を覚えているのです。
17節に「窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされないからです」とあります。ああ!私たちの祈りは、主の御前に、ないがしろにされてはいません。「主は私の祈りを顧みてくださった」と詩人の信仰の目は、「主とその御力」を、「その御名の力とあわれみ」を捉えたのです。 私たちも様々な苦しみで、心弱り、萎れてしまうことがあります。しかし、見上げてご覧です。夜の星ではありません。そこにいます主とその慈しみに目を留めて見上げるのです。すると、そこに私たちは見るでしょう。主が私たちのために備えてくださっている「いつくしみの時と定めの時」を見ることが出来るのです。
18節から22節の所を見ると、主の「いつくしみの時と定めの時」に目を注いだ詩人は、更に、後の世代の人々や諸国の民が真の救いを必要としている姿が見えて来たのです。そして、主の目がこれらの人々に上に注がれていることに気づいたのです。ついには、詩人の目は、人々が主の御名と主の誉れを賛美し、一つに集められ、主に仕え、礼拝する終末における幻をはるか彼方に見たのです。私たちも、詩人と共に、このような幻を見る者となりましょう。
三、変わることのない神御自身に目を注ぐ
23節からは、詩人は、再び自らの現状、弱さとはかなさとを思い、主に嘆き訴えています。しかし、以前のようにただ嘆き訴えるだけではありません。それと共に、詩人は、その目をしっかりと主の偉大さとその永遠性に目を留めています。私たちは有限な存在であり、弱くはかない存在であることを認めつつも、私たちの信じより頼む方は、代々にいます力ある方であり、そのご存在は変わることなく、永遠から永遠にいます方であることを告白しましょう。
28節に、「あなたのしもべたちの子らは、住まいを定め、彼らの裔は、御前に堅く立てられます」とありますが、私たちはどこに私たちの住まい、落ち着きどころを定めるのでしょうか。
最後に申命記33章27節をお開き下さい。「いにしえよりの神は、住まう家。下には永遠の腕がある」とあります。永遠の神が、私たちの住まうべき家だというのです。そして、どのような状況の中でも、私たちの下には変わることのない永遠の御腕があって、しっかりと支えてくださっているというのです。
(結論) 私たちも、この詩人のように、私たちの周りの状況が如何に移り変わろうとも、変わることのない永遠のお方である主に目を留め、愛する主ご自身を私の住まい、避け所とさせていただいて歩んでまいりましょう。