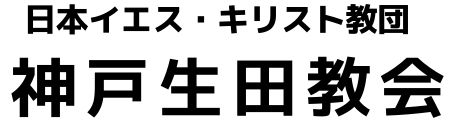礼拝説教「暗黒と荒廃の中に立つ十字架」2021年10月24日
聖書 詩篇89篇38~52節
(序)先々週は、詩篇89篇1~18節より「喜びの叫びを知る民」という題でお話しし、先週は、「ダビデへの恵みの契約」ということでお話ししました。そして、この詩は、「嘆きの歌」と呼ばれ、賛美で始まって嘆きで終わっていますと申し上げましたが、特に本日取り上げる詩篇89篇38~52節は、油注がれた者の苦難と恥と恥辱が描かれています。
一、油注がれた者の苦難を嘆く 38~45節
「恵みのまことが御前を進み、…喜びの叫びを知る民が、喜び叫びつつ、…御顔の光の中を進む」という祝福、そしてダビデに与えられた変わることのない契約は、38節に至って、暗転しています。
「しかし、あなたは拒んでお捨てになられました。あなたは、激しく怒っておられます。」(38節)今や、詩人の目には、「よろず備わって確かなとこしえの契約」は、神様に対するイスラエルの罪と反逆のゆえに、破棄されてしまったと思えたのです。
「油注がれた者」とは、ダビデの血を受け継ぐ王を指しています。イスラエルの罪のゆえに、主なる神は、激しく怒り、契約を破棄し、「油注がれた者」の王冠を地に投げ捨て、神の都であったエルサレムの城壁も打ちこわし、廃墟とされました。敵は勝ち誇り、「油注がれた王」の輝きは消え失せ、そしりの的となり、生気に満ちた若き日はあっという間に過ぎ去り、恥で覆われているというのです。
これは、エルサレムは焼け落ち、ユダ王国は滅び、王をはじめ人々がバビロンに捕囚として連れて行かれるという現実の苦難を嘆き歌っているのです。
二、空しい自らの生涯を嘆く 46~48節
38~45節で、詩人は、王国と王の上に下った厳しい破滅の現状を嘆きましたが、46~48節では、他人ごとではない、自分の身に降りかかる破滅と死におののき、空しい自らの生涯を思って嘆いているのです。
国の荒廃している現状の中で、詩人は、空しい自らの生涯を嘆き、「いつまでですか。主よ。あなたがどこまでも身を隠され、あなたの憤りが火のように燃えるのは。心に留めてください。私の生涯がどれほどかを」
(46~47節)と嘆いています。
48節、「生きていて死を見ない人は、だれでしょう」(48節)と自らに問いかけています。そんな人はだれもいない。誰もが死を経験するんだ。例外なく、この私もという事です。
「だれが自分自身を、よみの手から救い出せるでしょう」(48節)とありますが、私たちは、いかなる者も、自分自身を、よみの手から救い出すことはできません。
ローマ人への手紙3章23~24節、6章23節をご覧ください。「すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず。神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、価なしに義と認められるからです」(ローマ人への手紙3章23~24節)とあります。また、ローマ人への手紙6章23節には、「罪の払う報酬は死です。しかし、神の賜物は、主イエス・キリストにある永遠のいのちです。」(ローマ人への手紙6章23節)
とあります。
三、回復を求める祈りと油注がれた者の苦難 49~51節
49~51節において、詩人は、神様の「恵みとまこと」に目を留め、しがみつくようにして、王と王国の回復を切に祈り求めています。
「主よ。あなたのかつての恵みはどこにあるのでしょうか。あなたは、真実をもって、ダビデに誓われたのです」(49節)と主に向かって嘆き、叫んでいます。そして、すべての嘆きと祈りが、終わりへと向かって行き、ついに51節の結びの言葉へと集中して行きます。すなわち、「油注がれた者の苦難」の言葉で、この詩は結ばれるのです。そして、この「油注がれた者の苦難」という結びの言葉は、循環的に1~2節にあるこの詩の主題「主なる神の恵みとまこと」へと立ち返るのです。
詩人は、信仰者として、どの様なことがあろうとも、主なる神への信仰と信頼を失いません。
52節は、この詩篇89篇の結びの言葉というより、詩篇73篇から始まる詩篇の第三巻の締めくくりの言葉です。バックストン先生は、『詩篇の霊的思想』の中で、「第3巻は、レビ記と符合しており、『霊的暗黒と交わり』を題目としている」と記しておられます。
四、暗黒と荒廃の中に立つ十字架
さて、51節について、「油注がれた者の苦難」ということを申し上げましたが、それは、はるか後に「ダビデの子孫」として現れなさるメシア、すなわち主イエス・キリスト様のご苦難を指し示しています。
マタイの福音書16章21~25節とコリント人への手紙第Ⅰ 1章18節をご覧ください。今祈祷会では、福音書からキリスト伝、すなわち主イエス・キリスト様の地上のご生涯を学んでいます。この箇所は、主イエス様が十字架の予告をしておられる箇所です。主イエスは、私たちの罪のために十字架の苦難をお受けくださり、復活して、私たちの救いを成就してくださいました。ですから、パウロは、「十字架のことばは、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です」(コリント人への手紙第Ⅰ 1章18節)と言っています。
聖歌397番に「遠き国や」という賛美があります。この賛美は、日本語教師として来日していたJ.V.マーチンというアメリカ人宣教師が、関東大震災の直後、1923年9月の余震の続く夜、明治学院の校庭を訪れた時、被災者の人たちに支給された蚊帳の中で、揺らめくロウソクの灯が十字架に見えたところから、この詩を作った、と言われている賛美です。
折り返しには、「慰めもて汝がために、慰めもて我がために、揺れ動く地に立ちて、主の十字架は輝けり」と歌われています。そうです。いかなる暗黒と荒廃の中にも、主の十字架は輝いているのです。
(結論)先ほども申しましたが、「油注がれた者の苦難」という結びの言葉は、循環的に1~2節にあるこの詩の主題「主なる神の恵みとまこと」へと立ち返るのです。いかなる暗黒と荒廃の地にも主の十字架は立っており、輝いているのです。このことを思い、どの様なことがあろうとも、主なる神への信仰と信頼を失うことなく、主を賛美しつつ前進しましょう。