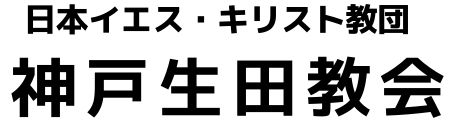礼拝説教「今の時を生かして」2022年7月31日
聖書 コロサイ人への手紙4章2~6節
(序)ここにパウロのこの手紙の最後の勧めがあります。
一、たゆまず祈りなさい
パウロは、2節で「たゆみなく祈りなさい」と目を覚まし、感謝をもって祈り続ける事を勧めています。
- 注目すべき第一のことは、「感謝をもって」という事です。「祈る」ということの中に信仰を見ることができます。「祈り」は、呟きや、不平、非難の言葉であるはずがありません。私たちは、祈ったことは、神様がかならず応えて下さると信じて祈ります。ですから、祈るとき感謝が溢れるのです。祈りは、その中心に、神様のご存在を置いて祈るべきです。私たちは祈るときに、まず「天の父なる神様」と呼びかけ、すべての願いを申し上げます。祈りの内容は、感謝の祈りであり、願いの祈りであり、悔い改めの祈りであり、信仰の祈りです。そして最後に、主イエスの御名によって祈ります。主イエス様が私たちの祈りを父なる神様に執成してくださるからです。
- 次に「たゆみなく」あるいは「たゆまず」という言葉に注目してください。「たゆみなく」とは、「ひたすら心を込めて」ということです。心を込めて熱心に祈り続けるときに神様は、必ず聞いて下さいます。ヤコブの手紙5章17節には、「正しい人の祈りは、働くと大きな力があります」とあります。主イエスの御名によって、熱心に祈り続ける時に、主は聞いてくださるのです。
- 第三のことは、「福音宣教のための祈り」ということです。パウロは、「キリストの奥義を、語るべき語り方で明らかに語れるように祈ってください」と祈りの要請をしています。もちろん人生の諸問題、日常の細々としたことの全てを神様は聞いて下さいます。しかし、なによりも私たちが、心を込めて祈るべきことは、「神のみことばの宣教」ということです。多くの人々が、真の神様を知らず、主イエス様の十字架による救いをを知らないで、様々な苦難を抱えて苦しんでいます。そのような悲惨な状態から救われる福音を知らせるために何よりも祈る必要があるのです。
二、機会を捉えて
5節に「機会を十分に生かし、知恵をもって行動しなさい。」とあります。私たちは、時が良くても悪くても、主のみことばを伝えねばなりませんが、祈りつつある中で、今こそがチャンスだという時が教えられます。その時を、私たちは、生かしたいと思います。
5節の「機会を十分に生かし」とは、エクサゴラゾーという言葉が使われています。それは、「贖う」という意味をもった言葉です。ですから、「時を贖いなさい」と言うのです。私たちには、日ごとにしなければならないことが多くあります。何年か前、ある先生が、こんなことを言っていました。すなわち、「昔は、今よりもずっと寿命が短かったにもかかわらず、世の中が便利になると同時に、せかせかと忙しくなって来ている。新幹線に乗って何度も東京と神戸の間を往復しているが、ほんの数えるほどしか同席の人と話をしたことがない。昔は、同席の人と自己紹介をし、行く先を尋ねたものです。いつも、そこには出会いがあり、実にそれは旅でした。しかし、今は、ビジネスであって、旅が失われている」と仰っていました。全く同感です。
私たちは、大切なものがなんであるかを見失わないようにしたいと思います。今は、新型コロナの感染拡大によって、人と人の交わりがさらに希薄になってしまいました。しかし、それだけに多くの人々が不安を感じています。このような時にこそ、神様の導きと知恵を求め、人々に福音の恵みを証しさせていただきましょう。文語訳では「機会をうかがい」とありました。いつでも機会を捉えようとしていなければ、機械は失ってしまいます。折角のチャンスを失うことなく、大切に生かしたいと思います。
<例話あかし>時を失うな:安木末治君のこと:2テモテ4:2
中学3年生の時でした。家の事情で遠くの町の工場に就職した友人に、卒業式の時、聖書を渡して、「末ちゃん、手紙をまた書くからなあ」と約束して別れました。2~3回手紙のやり取りをしました。しかし、自分のことが忙しくて、返事を書くのを怠ってしまいました。それからというもの、プッツリと連絡が途絶えてしまいました。それからしばらくして、私の耳に入って来たのは、「末ちゃんが、亡くなったそうな」という風の便りでした。私は、「しまった!あの時、彼に返事を書いていれば、こんなことにはならなかったのに」と自らの失敗を悔やみました。しかし、どうすることも出来ません。ああ皆さん。皆さんにも、あなたでなければ福音を伝えることの出来ない人がいるのです。どうぞ時を逸することのないようにいたしましょう。
三、幾人かを救うため
6節をご覧ください。「あなたがたのことばが、いつも親切で、塩味のきいたものであるようにしなさい」とあります。私たちは、「神のことば」に真実と力と救いがあると信じています。それを伝えるに当たって伝える私たちの語る言葉が大切です。「いつも親切で、塩味のきいたものであるようにしなさい」と言うのです。聖書協会共同訳では、「いつも塩味の効いた快い言葉で語りなさい」とあります。「親切なことば」「快い言葉」とは、恵みの言葉です。私たちは、つい話しに夢中になって、一緒に怒ったり、落ち込んだり、他の人を批判したりしてしまいます。しかし、私たちの会話が、いつも神の恵みで溢れ、人を慰め、励まし、希望を与える言葉でありたいと思います。それこそが、だれでも聞きたいと望んでいる言葉です。また「塩味の効いた」とあります。塩は①腐敗を防ぐ働きをし、②料理の味を調える働きをします。ですから「塩味のきいた言葉」とは、人々の心に、健全で恵みに溢れ、生き生きとした感動を呼び起こす言葉です。そのような、「塩味のきいた言葉」は、人を生かすのです。マタイの福音書5章13節には、「あなたがたは地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです」とあります。私たちは、人をむやみに批判する辛らつな言葉を語るべきではありません。しかし、ただ人が喜ぶような甘いだけの言葉でもいけません。それは、人々をだめにしてしまいます。ですから、私たちは、いつも何を語るべきかを神様に教えて頂きながら人々を生かす言葉を語りたいと思います。
(結論)心を込めて祈り、機会を捕らえ、幾人かでも救うために、私たちの唇をきよめて頂き、いつでも「親切で、塩味のきいた言葉」を語る者でありたいと思います。せっかくの機会を失うことのないようにいたしましょう。