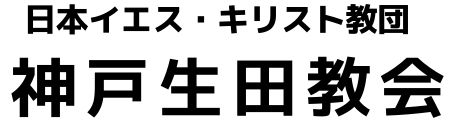礼拝説教「ことばの受肉」2023年12月17日 アドベント第3週
聖書 ヨハネの福音書1章9~14節
(序)ヨハネによる福音書は、限られた一つ一つの鍵になる言葉に、深い意味を込めて語っていますが、「栄光」もそのような鍵になる言葉の一つです。そこで、本日は、1章14節の「栄光」という言葉を中心に見てまいりたいと思います。「栄光」とは何でしょうか。栄光とは「神の隠された本質が外に現わされたものです。」
- 「まことの光」としての「ことばの受肉」
「神」としてのご本質と御力をもたれた「ことば」である方が、人となってお生まれ下さった、それを「受肉」と言います。それは驚くべき事実です。受肉は、人間の誕生には決して用いません。人間は、はじめから地上の肉に属する者だからです。「受肉」と言われる時に、本来絶対他者である神が、被造物としての肉体を取ってくださったことが表明されています。これほどに驚くべき事実はありません。しかも、受肉は、十字架と復活の出来事へと連続しており、「贖い」の前提であり、土台です。
9節は、理解の分かれる難しいところですが、私は、「すべての人を照らすまことの光が世に来ようとしていた」「…来つつあった」と理解するのが良いだろうと思います。すなわち、ここには、まことの光であるイエス・キリストが、徐々に現れ、その輝きとその御存在をいよいよ明かにされて行く様子を読み取ることができます。暗黒の地に一条の光が射し、預言者たちによって証しされることによって、その輝きを増し、メシアを証しする最後の預言者としてバプテスマのヨハネが登場し、その御名を信じることによって、個人的に救いの体験として、私にまでおよぶところの「まことの光」としての「ことば」、主イエス・キリストの降誕が証しされているのです。そしてついに、14節に至って、受肉の事実とその栄光について述べられています。
「ことばの受肉」という事実が、私たちに明らかになった時、私たちはそこに「父の独り子」としての栄光を見るのです。それは、「めぐみとまこととに満ちておられた」というのです。まさに、「めぐみとまことに満ちた」みことばが、私たち一人ひとりに届いたからこそ、私たちは、主を信じることができたのではないでしょうか。その意味において、宣教は、ミッシオ・デイ(神の宣教)と言われますように、神様のハートから出て、神様の御手によってなされる神様ご自身の御業です。私たちは、そのお手伝いを任されている者に過ぎません。ですから、主の栄光が現わされ、人々に、みことばの恵みと真実が伝わるように、私たちの務めを果たさねばならないし、また、果たさせて頂けば、主ご自身が働いてくださるのです。
二、めぐみとまことに満ちた栄光
ヨハネ1章14節を御覧ください。その「栄光」は、「めぐみとまこととに満ちていた」というのです。主イエスの「栄光」は、「恵みに満ちた栄光」でした。すなわちそれは、救済的・贖罪的栄光と言っても良いのではないでしょうか。栄光とは「神の隠された本質が外に現わされたものである」と申しましたが、さらに言い換えるならば、「栄光」とは、「神の恵み、変わることのない神の愛という本質が輝きだしたもの」です。ヨハネ2章におけるカナの婚姻の奇跡のように、主は、私たちが欠乏を覚えた時、その必要に応えて下さる方です。ここに「ことばの受肉」の意義があります。すなわち、「ことばの受肉」によって、主の「めぐみとまこと」を知らせていただいたということです。違う言い方をすれば、「神ご自身が私たちの弱さを知って下さり、私たちを『めぐみとまこと』をもって救って下さる」ということです。
主が「受肉」してくださったということは、その救いが、絵空事ではなく、実に、主ご自身が、歴史の中に、まさに様々な出来事が起る私たちの生活のど真ん中に足を踏み入れてくださり、暗黒と苦しみの中から、私たちを救い出してくださる方となってくださったということです。
それゆえ、私たちは、みことばを伝え、伝道しようとする時、大切なのは、相手の方の必要を見出し、それに的確に応えているみことばの恵みを伝えることです。相手の方の必要を見出し、主とそのみことばが、如何に真実であるかを伝えることは伝道する場合大切なことです。ですから、そのためには、まず、私たち自身が、日々に、みことばに生き、また生かされているという証を持ちたいと思います。今も、御霊様は、働いてくださって、御言葉を魂の奥底に届かせてくださるのです。
三、恵みに恵みを加えてくださる栄光
最後に、「恵みに恵みを加えてくださる栄光」ということについて申し上げたいと思います。16節に、「私たちはみな、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けた」とあります。
この「上にさらに」というのは、アンティと言いまして、通常「向って」とか「反対」という意味を持っていますが、ここでは、「代りに」というような意味で用いられています。丁度、売り買いするときに物と物、物とお金を交換しますが、そのような時に用いる「代りに」という意味で使われています。つまり「恵みに代えて恵みを」というわけです。
A.T.ロバートソンは、このことを「毎朝新鮮なマナに与っていたように、日ごと、また毎回の礼拝において新たな恵みに与ることである」と言っています。主イエスは、このような恵みとまことの満ち満ちた豊かさをもって、私たちを養ってくださいます。
み言葉に、「主のいつくしみは絶えることがなく、そのあわれみは尽きることがない。これは朝ごとに新しく、あなたの真実は大きい」(口語:哀歌3:22~23)とあります。まさに、主は朝ごとに慈しみと真実(ヘセッドとエムナー)をもって、私たちを生かしてくださいます。主イエスは、満ち溢れる恵みとまことをもって、私たちを養ってくださり、ご自身の臨在を明かにしてくださるのです。
愛と真実の主のみことばを、私たちの内にしっかりと宿らせ、み言葉に生かされ、みことばに生きる者となりましょう。
(結論)現代は、「みことばを聞く飢饉」の時代であると思います。携帯電話で、いつでも、どこでも、相手と話をすることが可能となりましたが、便利さと引き換えに、本当のことばの力、ことばのいのちを失った時代ではないでしょうか。この様な時代に、ことばの受肉ということは、これまで以上に求められていると思います。キリストの言葉を内に宿し、内住のキリストの恵みに生きて、人を本当の意味において生かす働きに参与させていただこうではありませんか。