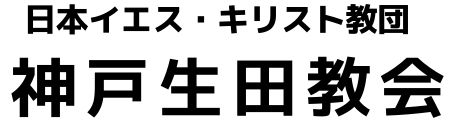礼拝説教「恵みと豊かな贖い」2023年8月13日
聖書 詩篇130篇1~8節
(序)捕囚より回復後の作と思われています。七つの悔い改めの詩篇(6篇、32篇、38篇、51篇、102篇、130篇、143篇)の一つに数えられています。
- 深い淵から(1~4節)
1節、詩人は、「深い淵から私はあなたを呼び求めます」と主のあわれみを求め、主に向かって祈り求めています。まさに私たちは、かつて深い淵のような暗黒の中でもがき、苦しみ絶望の淵をさ迷っていた者です。
2節、「私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください」と主を呼び求める願いの声をますます大きく上げています。
3節、詩人は、「あなたがもし、不義に目を留められるなら、…だれが御前に立ちえましょう」と自らの罪深さを覚え、ただ、主のあわれみを求めているのです。
4節に「しかし、あなたが赦してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます」とあります。詩人は、悔い改めの叫びを上げるだけではありません。主の赦しの恵みに目を向けています。新共同訳には、「しかし、赦しはあなたのもとにあり、人はあなたを畏れ敬うのです」とあります。この訳のほうが意味を理解しやすいと思います。とにかく、詩人は、悔い改めの叫びを上げるだけではなく、主に顔を向けて、主の赦しを待ち望んでいます。私たちも主に私たちの目と思いを向け、主を待ち望む者となりましょう。
- 主とそのみことばへの待ち望み(5~6節)
5節、「私は主を待ち望みます。私のたましいは、待ち望みます」と、詩人は、主を切に待ち望んでいます。主とそのみことばを待ち望んでいるのです。6節、詩人は、どれほど切に主を待ち望んでいるかを、夜回りが夜明を待つ様子と比較して述べています。夜回りは、眠気と戦いながら、夜明のくるのを待ちます。その様に、「主を心から待ち望む」と言うのです。
私たちも静かに主とその救いを待ち望むということは大切です。何か神様のみこころを求めるときもそうですが、日々の生活の中でみことばを待ち望みましょう。特に礼拝において私たちが恵まれる秘訣は、待ち望むことです。
三、主のもとにある恵みと豊かな贖い 7~8節
7~8節には、贖いの恵みに与った者の喜びの叫びがあります。
詩人は、1~4節で魂の叫びを上げ、5~6節で主とそのみことばを待ち望みましたが、7節より、イスラエルの民に向って「イスラエルよ。主を待て」と呼びかけています。主の贖いの恵みに与った者は、その恵みを自分だけのものとはしません。必ずその恵みを誰かに伝え、共に喜びたいと思うものです。ですから、詩人は、「主には恵みがあり、豊かな贖いがある」と人々に自分の体験を証ししているのです。詩人は、主の贖いの恵みの豊かさ、確かさを人々に伝え、「イスラエルよ、主を待て」と勧めています。
エペソ人への手紙2章1~9節をご覧ください。ここに引き上げる救いが書かれています。1~3節は、私たちがかつては背きと罪の中に死んでいた者であることが述べられています。私たちは、罪の中にあって浮きつ、沈みつ、世の流れに流されていた者であり、空中の権威を持つ支配者すなわちサタンに惑わされ、自分の欲のままを行い。神の御怒りを受けるべき者でした。
しかし、4節にあるように、神の豊かなあわれみのゆえに、救われ、生かされ、引き上げられて天の所に座るところの者として頂いたのです。ルターは、130篇に基づいて、「貴き御神よ、悩みの淵より 呼ばわる我が身を 顧み給えや。み赦しうけずば きびしきさばきに たれかは堪うべき」(讃美歌258)と歌っています。「この恵みのゆえに、…信仰によって救われたのです」(エペソ人への手紙2章8節)とあるとおりです。実に、「主には恵みがあり、豊かな贖いがある」(詩篇130篇7節)のです。
そして、8節に至って、詩人は、「主は、すべての不義から、イスラエルを贖い出される」と確信にあふれてイスラエルに呼びかけています。
私たちも贖いの喜びに満たされ、主とその救いを大いに証しする者となりましょう。
(結論)かつては深い淵のような暗黒の中でもがき苦しんでいましたが、主の救いの恵みに与った者として、この救いの喜びを人々に証ししましょう。