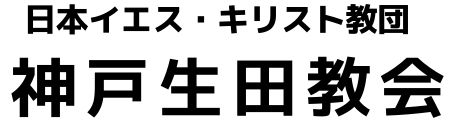礼拝説教「受け継いだ信仰の遺産②―聖化の恵みー」
2023年8月6日
聖書 ガラテヤ人への手紙2章19~20節
(序)本日は、「受け継いだ信仰の遺産」ということで、「聖化の恵み」について共に見て参りたいと思います。
一、罪からの二重の癒し
まずコリント人への手紙3章1~3節をご覧ください。パウロは、ここでクリスチャンを二種類に分けています。すなわち、「御霊に属する人」と「肉に属する人」です。「肉に属する人」は、幼子のようなクリスチャンであり、堅い食物を食べることができず、乳を飲んでいるような者だと言うのです。肉に属する人は、生活の基準をキリストでなく、世の基準に置こうとします。しかし、御霊の人は、キリストを基準にするのです。ガラテヤ人への手紙5章16~26節には、「肉のわざ」と「御霊の実」が対照的に記されています。肉の働きは、「淫らな行い、汚れ好色、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、ねたみ、泥酔、遊興」とあり、御霊の実は「愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制」とあります。キリストを信じて罪赦されても、私たちの内に、肉の性質、古き人が残っているのです。先ほど賛美しました新聖歌229番「千歳の岩よ」の1節に、「千歳の岩よ わが身を囲め 裂かれし脇の 血潮と水に 罪も汚れも 洗いきよめよ」とあります。そしてこの1節の原歌には、Be of sin the double cure とあります。すなわち、「罪からの二重の癒し」ということです。十字架で流してくださった主イエスの血潮は、犯して来た罪も、肉の性質としての罪も二重に癒しきよめてくださるのです。
二、キリストと共に死に、共に生きる
ガラテヤ人への手紙2章19節に「私はキリストとともに十字架につけられました」とあります。キリストの十字架は、「私のための十字架」であるとともに、「私をともにつけてくださる十字架」でもあります。私の罪を赦し、咎をきよめてくださる「私のための十字架」ですが、同時に、自分ではどうすることも出来ない肉の性質としての自我、古き人を、「キリストと共につけてくださる十字架」なのです。ローマ6章をご覧ください。
パウロは、6章より聖化の恵みについて述べています。3~4節に、パウロは、バプテスマの原理をもちだして、聖化を説明しています。すなわち、バプテスマとは、「古き人が、キリストとともに死んで、新しくキリストとともに生きること」を目に見える形において表している儀式です。パウロは、このバプテスマの意味を用いて、キリストとともに死に、キリストとともに生きるという聖化の恵みを述べているのです。
「キリストとともに死に、キリストとともに生きる」という聖化の恵みにとって大切な三つの言葉を心に留めていただきたいと思います。すなわち、6節の「…知っています」と、11節の「…認めなさい」と、13節の「…献げなさい」の3つです。
1.知ること(6節)
まずは、「知ること」です。何を知るかというと、私たちの古き人がキリストとともに十字架につけられていることを知ることです。キリストの十字架の恵は、「私たちのための十字架」であると同時に、「私を共につけてくださる十字架」なのです。私たちの古き人が十字架にキリストとともにつけられていることを知ることです。
2.認めること(11節)
第二に11節の「認めなさい」ということです。この「認めなさい」と訳された言葉は、「計算する」という意味の言葉が用いられています。すなわち、古き人が十字架にともにつけられて、罪に対しては死んだ者であり、神に対してはキリスト・イエスにあって生きたものであることを、自分に当てはめて、「認め、計算しなさい」と言うのです。
3.ささげること(13節)
第3は、自分自身とその手足を「献ること」です。罪の奴隷となるのではなく、従順の奴隷、義の奴隷となって、恵の下にあって、聖潔へと進むのです。パウロがここで言っているのは、「全く明け渡して主に従い、主に合体し、キリストにあって生かされ」聖化の道を歩む者とされることです。
古き人がキリストとともに十字架につけられている事実を知りましょう。そして、その事実を自らに当てはめて計算し、認めましょう。さらに、己が身と霊をささげ、明け渡し、日々主と共に歩むのです。そこにきよめの恵みへの秘訣があります。
三、内住のキリストの恵み
ガラテヤ人への手紙2章20節をご覧ください。「もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。」私とキリストが対照されている不思議な一句です。直訳すると「だが私は生きています。もはや私ではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。」となります。「…死んだ」「…十字架につけられた」と言って来たパウロは、突然その方向を変え、「私が生きているのは、私ではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです」と今まで生きる主体であった私が生きているのではなく、キリストご自身が、主体となって、私のうちに、生きてくださる、と言うのです。パウロが、「キリストが私のうちに生きておられる」という場合、信仰者がキリストの体の部分として「キリストのうちにある」というよりも、さらに、「個人的な生き方が変革された」ということを表現しています。もはや、生きる主体が変わり、その歩みの始から終わりまで、キリストが主となってくださり生かされるというのです。まさに、これは、聖化の真髄であり、キリスト者の経験の極致と言って良いでしょう。
<例話>内住のキリスト:竹田俊造先生の一言:ガラテヤ2:20
竹田俊造先生の一言といえば、「キリスト我が内にありて生きたもうが聖めさ」であろう。神戸基督復興教会主催の聖会の後、お茶の間教室で、「ささげるとか、捨てるとか、従うとか、死んだとかいうのはきよめではないからなー」と俊造先生が言われたので、小島先生が「では何がきよめですか」と詰め寄られたそうです。すると、先生、少しも騒がず、「キリスト我が内にありて生きたもうが聖めさ」と言われた、と小島伊助先生が述懐しておられます。三島常夫先生からも同じようなお話をお聞きしたことがあります。三島先生が垂水教会で牧会伝道をしておられたある日、竹田俊造先生が訪ねて下さって、しばらくの交わりをしていただいた。その時、きよめについてお尋ねすると、丁寧にいろいろと教えてくださった。お帰りになって、数日して、再び竹田俊造先生がお訪ねくださった。「あんたに、言い残したことがある」と言われる。「何でございましょう」と申し上げると、「きよめとはキリスト我が内にありて生きいたもうだ、ということを言い残したので訪ねてきました」と言われた。「わざわざそのことを伝えに、お出でくださったことを、恐縮もし、感謝した」とお聞きしたことです。
(結論)そうです、私たちは、「キリスト我が内にありて生きたもうが聖めさ」ということを私たちの心の肉碑に刻み、これを私たちのもの、私たちの体験とし、「受け継いだ信仰の遺産」としましょう。