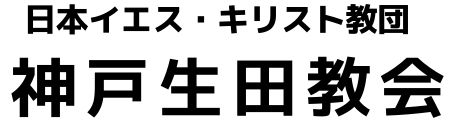礼拝説教「共にいて強めてくださる主」2021年7月25日
聖書 テモテへの手紙 第二 4章9~22節
(序)本日をもって、1月から読んでまいりましたテモテへの第Ⅰと第Ⅱの手紙からのメッセージを終えたいと思います。
一、パウロを取り巻く厳しさ
AD64年7月18日から約6日間にわたって、ローマに大火災がありました。それは、ローマ市街地の3分の2が焼失したと言われるほどの大火でした。皇帝ネロがこれを行ったといううわさが立ち、この風評を打ち消すために、ネロはキリスト者に罪を着せ、大迫害が起こったのでした。
その迫害の中で、パウロとペテロは、殉教したと伝えられています。先週は、「私の世を去る時が来ました」と言うパウロの覚悟を見ましたが、本日は、パウロが、もう時の猶予のないことを知って、テモテに何とかして早く来てくれるようにと要請している箇所です。
10節から、パウロは、自分の近況について述べています。「デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまいました。」(10節)デマスは、パウロと共に伝道旅行に同行していた同労者でした(コロサイ4:14、ピレモン24節)。その彼が、パウロを捨てて、「テサロニケに行ってしまいました」(10)とかなりパウロに大きな痛手を負わせた様子が見て取れます。
しかも、「デマスは今の世を愛し」と言うのです。この「愛する」という言葉は、「愛」という意味のアガペーの動詞形アガパオーが使われています。このアガペーが、神様の愛に用いられる場合には、神様の意思的、一方的、「無私の愛」、「にもかかわらずの愛」を意味しています。ところが、ここにおいては、誰の言葉にも耳を貸さないで振り切るようにして一直線に突き進むデマスの態度を示しています。デマスは、共にいてパウロを助けるのではなく、振り切るようにして、パウロを見捨て、彼の故郷であったかもしれない「テサロニケに行ってしまった」と告げているのです。
また、同じ10節に出て来るクレケンスは、ほかの聖書の箇所には出てこない人物です。彼は、ガラテヤに行きました。(他の写本では、ゴールとなっており、ゴール地方、今のフランスに行ったとの説もあります。)
テトスは、クレテで伝道していた時に、パウロより、テトスへの手紙を受け取っています。その後、パウロに同行しましたが、イルリコ(ローマ15:19)の南部ダルマテヤに派遣されたのだろうと思われます。
14節には銅細工人アレキサンデルが出て来ます。彼は、おそらく第1テモテ1章20節に出てくる正しい良心を捨てて、信仰の破船にあったアレキサンデルと同一人物と思われます。彼は、パウロを「ひどく苦しめ、激しく逆らった、だから彼を警戒しなさい」と言っています。
16節で、パウロは、他の自分を見捨てた人々に対して、彼らが裁かれることのないようにと執り成し祈っています。
二、冬になる前に
パウロの下からある者は去り、ある者は派遣されて、今やパウロの下には、ルカしか残っていません(11節)。ルカは、コロサイ人への手紙4章14節では、「愛する医者ルカ」と言われています。とにかく、
テモテへの第2の手紙4章9節以降には、テモテの到着をしきりに待っているパウロの姿があります。
そしてパウロは、テモテが来る時に、マルコを連れてくるようにと要請をしています(11節)。マルコは、バルナバのいとこであり、福音書を書いています。彼は、パウロの第1回伝道旅行のとき、途中から逃げ帰っており、パウロの第2回伝道旅行に際しては、マルコのことで、パウロとバルナバとの間の意見が合わず、彼らが別々の道に進んだ経緯のある人物です(使徒の働き15:37~39)。しかし、後に、パウロにその有用さが認められ(コロサイ4:10)、ここでは、「マルコを伴って、一緒に来てください。彼は私の務めのために役立つからです」とテモテに要請しているのです。
とにかく、パウロは、この手紙において、「何とかして早く私のところへ来てください。」(9節)「マルコを伴って、一緒に来てください。」(11節)「外套を持って来てください。…羊皮紙の物をもって来てください」(13節)と再三テモテの早く来てくれるのを待ち望んでいます。
21節においても、プリスカとアキラ(アクラ)、オネシポロの家族への挨拶とエラスと、トロフィモの消息、ユブロ、プデス、リノス、クラウディア、すべての兄弟たちからの挨拶を記した後に、再度「冬になる前に来てください」とテモテが早く来てくれるようにと要請をしています。
パウロを取り巻く状況の厳しさやテモテの到来を待っているパウロの心情を考えると、時の切迫していることを覚えさせられます。
「みことばを宣べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。」(4章2節)とあるごとく、私たちも、やがて冬の時代が来ることを覚え、福音宣教に励みたいと思います。
三、共にいて、強めてくださる主
しかし、そのような中にあっても、パウロは、「主は、私とともに立ち、私に力を与えてくださいました」(17節)と、主への感謝と信頼を言い表し、主に賛美をささげています。いかなる困難な時にも、主は、パウロと共にいて、彼を力づけ、強めておられます。
同じように、私たちがいかなる困難の中にあっても、たとえ最期の息をする時にでも、共にいて強め力づけてくださるのです。
続いて17節の後半において、「それは、私を通してみことばが余すところなく宣べ伝えられ、すべての国の人々がみことばを聞くようになるためでした」とパウロは、常にみことばを宣べ伝えることに焦点を合わせています。私たちも、私たちの生涯の目標として、一人でも多くの人に、主を証しする者となりたいと思います。
18節、「主は私を、どんな悪しきわざからも救い出し、無事、天にある御国にいれてくださいます。主に栄光が世々限りなくありますように。アーメン」と御国への確信と主への頌栄をささげています。
22節において、主の臨在がテモテと共にあり、恵みが兄弟姉妹たちと共にあるようにと最後の祝祷をもって筆を置いています。
私たちも、共にいて強め力づけてくださる主を仰ぎつつ、時が良くても悪くても、みことばを宣べ伝えて参りましょう。
(結論)いかなる困難の中にあっても、共にいて強め力づけてくださる主を仰ぎ、信仰の良き戦いをりっぱに戦い抜きましょう。「義の冠」、「いのちの冠」、「栄光の冠」は、そこに備えられています。
パウロと共に、「主は、私とともに立ち、私に力を与えてくださいました」(17節)と言うことの出来る者となりましょう。