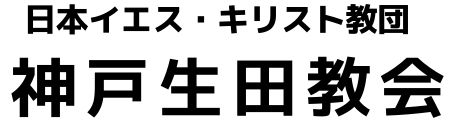礼拝説教「恵みによって強められ」2021年6月13日
聖書 テモテへの手紙 第二 2章1~7節
(序)本日もテモテへの手紙 第二 からお話し致します。
一、恵みによって強くなりなさい 1節
1章で、パウロは、テモテに、神の賜物として力と愛と慎みとの霊を与えられているのだから、主を証しすることや、パウロが福音のために囚人として捕らえられていること恥じてはいけません。むしろ、神の力によって、福音のために苦しみを共にして欲しいと言っています。
2章に入って、パウロは、テモテに対し、「キリスト・イエスにある恵みによって強くなりなさい(エンデュナモー)」と勧めています。
まず目を留めていただきたいのは、「キリスト・イエスにある恵み」です。私たちの力や知恵や努力で強くなるのではありません。私たちを強めてくださるのは、ただ「キリスト・イエスにある恵み」です。
そしてパウロは、「キリスト・イエスの立派な兵卒として、私と苦しみを共にしてください。」(第2テモテ2章3節)と言うのです。
私たちが、力と愛と慎みとの霊に満たされて、福音のために力を注いで、主に仕えて行くことの出来るのは、ただ「主イエスの恵み」によるのです。ですから、私たちは、主が私たちに絶えず注いでくださっている「恵み」に目を留め、「キリスト・イエスにある恵み」によって強くしていただきましょう。
小島伊助先生は「恩寵を知りわきまえることが霊魂を強くする。霊肉健在でなければ、どんなに近代武装しても役には立たない。自らが健全であって初めて精兵卒スピリットもものを言う」と言っておられます。
二、後継者の育成 2節
「働きは働き人」と言われますが、教会が継続して成長していくためには、後継者が備えられ、育成されて、働きがゆだねられ、継続して拡大されて行くことが大切です。ですから、パウロは、テモテに、後継者の育成を勧めると共に、このために背後にあって祈っているのです。
2節には信仰継承の働きが記されています。それは、まずパウロからテモテへ、次にテモテから彼の後継者へ、彼の後継者からさらに次の世代の後継者へと、さながら鎖のように、継承されて行くべきことが命じられています。これを見ると、パウロが、信仰の継承ということを非常に大切にしていたことがわかります。
私たちにとっても信仰の継承ということは非常に大切です。ぜひともこのために祈り、恵みによって強められて、信仰継承という私たちの責任を果たしてまいりましょう。
後継者として大切な教えを委ねるのに必要なのは、「教える力という賜物」と「忠実であるという信頼に満ちた人」です。
「教える力」とは、単なる知識を教える能力ではありません。みことばの真理を具体的、実際的、霊的、体験的に教えるの力です。もちろん聖書の知識や正しいキリスト教の教理や教会の歴史、さらには社会や人々の心の機微を知って教えることが大切です。しかし、最も大切な教える能力は、その人自身が福音の恵みを体験しているということです。
さらに、「忠実であるという信頼に満ちた人」とは、かつては信仰に熱心だったのですがというようなことでなく、変わることのない忠実な働き人であることです。そのような後継者の育成のために、私たちは、真剣に祈り、全力で投球して行かねばなりません。
三、働き人の姿勢 3~6節
「恵みによって強くされること」と、「忠実な後継者の育成」について言及したパウロは、働き人の姿勢を三つの譬えで説明しています。
①第1は、立派な兵士です。
「イエス・キリストの立派な兵士」とパウロは言っています。「立派な兵士」には、完全な忠誠、絶対的な服従、徹底した献身と自己犠牲、物事に動じない的確な判断力、死をも恐れない勇敢さが求められます。ロザハムは、Take thy part in suffering hardship, as a brave soldier of Christ Jesus <キリスト・イエスの勇敢な兵卒として、困難な苦しみという汝の分け前を取れ>と訳しています。
昨年頂きました『香登修養会60周年記念誌』の中に、佐藤邦之助先生の「キリストの精兵」と題する説教が掲載されていました。その中にこのようなお話しがありました。日露戦争の時のことです。旅順総攻撃の前に、一つの大事な任務が生じたそうです。そこで、乃木希典(のぎまれすけ)大将は勇士を募りました。すると80数人の勇士が志願して出て来ました。彼らは、乃木大将の周りをぐるりと取り巻き、「閣下、どうか私をやってください」としきりに願いました。人があまりに多かったので、さて誰をやろうかと物色している時に、裏の方から「ちょっとごめんなさい。ごめんなさい」と言いながら人をかき分けて出てきた人物があった。何とこれは、白衣の勇士。野戦病院でさっきまで寝ていた兵隊です。胸を病んで片足棺桶の中に突っ込んでいるような、哀れな生ける屍同然の白衣の兵士です。彼は、乃木大将の前に出て来て、「閣下、お願いですから、私をやっていただきたい」と言った。乃木大将はびっくりして、「えっ!お前が行こうと言うのか?本気かそれ!」「本気です。どうか私をその任務にやらしてください。」野木大将、彼を上から下まで静かに見て、しばらく目を閉じていたかと思うと、目をぱっちりと開けて言ったというのです。「そうかい、お前、行こうと言うのかい。うふん!よし、それじゃ頼むぞ。行って武装してこい。」「やらしてくださいますか。ありがとうございます」と言ったかと思うと、挙手の礼も忘れて、野戦病院に帰って行き、やがて、やせた体にダブダブの武装をして、乃木大将の前に戻って来ました。「何も足りないところはないな。よしそれじゃ、お前に行ってもらおう。ちょっと来い」と命令の内容を小声で話し、「分かったか。」「分かりました。」「じゃ行って来い。」「はぁただいまから行って参ります。」こう言って彼は、不動の姿勢で挙手の礼をして、回れ右をしたかと思うと静かに闇の中に消えて行きました。心穏やかでないのは、志願して参りました80名ほどの兵士たちです。「閣下、どういうわけであんな者をおやりになったのですか」と迫ってまいりました。この時、乃木大将、「あのね、お前たちにはわからんだろう。あれになぁ死ねる場所を与えてやったのだ。彼は二度と帰って来ん。お前らもそうだろう。せっかく内地から出て来て、野戦病院で野たれ死にしたくないだろう。華々しく死にたいだろう。それであれに死に場所を与えてやったのだ。あれは戻ってはこん。戦死するに決まっている。お前らにはまだこれから死に場所はたくさん残っている。そうだから頼むぞ。いいか。」
それを聞いて80名ほどの兵士たちは、闇の中に消えていった兵士の後ろ姿に向かって脱帽し、目から涙をこぼしたそうです。
その兵士は、苦難という分け前を受け取ったのです。私たちも、私たちの愛する主イエスから、苦難という分け前を受け取っらせて頂こうではありませんか。ピリピ人への手紙1章29節には、「あなたがたがキリストのために受けた恵みは、キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです」とあります。すなわち「キリストのために、…苦しむことをも賜っている」のです。そして良い兵卒は、日常生活のことに心を奪われてはいません。ただひたすらに、召した者を喜ばせようとしているのです。
②第2は、栄冠を得る競技者です。
当時、ギリシャでは都市ごとに競技会が開かれ、勝者には、月桂樹の冠とか、松の冠とかが贈られました。彼らは、競技に先立ち一定期間、厳しい練習をしなければならないという約束やその他の細かい規定がありました。競技者は、その規定に従って練習し、また競技しなければ栄冠を得ることは出来ません。
私たちも、一見、勝った、成功したと思っても、最後の審判のときに、反則が認められ、失格となることの無いように励みましょう。
③第3は、労苦する農夫です。
農夫は、暑さ寒さをものとしないで、土を耕し、種を蒔き、苗を育て、ついに収穫の喜びにあずかります。苦労して農作業に精を出さないで放っておいては、収穫は期待できません。そのように、労苦する農夫こそ第一に収穫の分け前にあずかるのです。「農夫は、労と恵みと望みのよい模範である」と小島伊助先生は言っておられます。
詩篇126篇5~6節をお開き下さい。「涙とともに種を蒔く者は、喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え、泣きながら出て行くものは、束を抱え、喜びながら帰って来る。」(詩篇126篇5~6節)
(結論)「キリスト・イエスにある恵み」によって強くされ、後継者からさらに次の世代の後継者へと、信仰継承の働きに努め、「イエス・キリストの立派な兵士」「栄冠にあずかる競技者」、「労する農夫」としての信仰生涯を励みましょう。その時、見失ってならないのは、「キリスト・イエスにある恵み」によって強くされるということです。