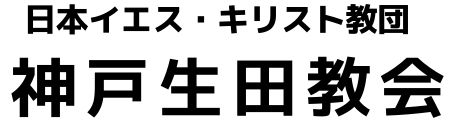礼拝説教「時を失うことなく」2021年2月14日
聖書 テモテの手紙第二4章2節 (新改訳2017)
(序)本日は、この年の教団標語に選ばれています。もう一つのみことばからお話するように導かれています。
一、厳かな命令 1節
まず1節からご覧ください。パウロは、第1の手紙5章21節でも、神の御前において、厳かに命じていますが、ここでは、「生きている人と死んだ人をさばかれるキリスト・イエスの御前で」と、最後の審判の時を覚えて厳かに命じています。この手紙は、パウロの絶筆であり、いよいよこの地上における終わりのときの近いことを知って、パウロは、キリストの臨在とその再臨を実感し、永遠の審判者であるキリスト・イエスを仰いで、厳かに命じているのです。
「その現れ」とは、キリストの再臨を指しています。「その御国」とは、キリストの再臨によって出現する御国です。今はどのような状況にあったとしても、パウロは、神がご支配される御国にをはっきりと目の前に見、御国に対する希望を望み見て、このように言っているのです。
私たちは、思い違いをしてはいけません。私たちには、その日その時がいつであるかはわかりませんが、この地上の営みはいつまでも続くものではないのです。いつか終わりの時が来るのです。主イエスが再びお出でになり、新しい天と地が出現するのです。その時までに、私たちの愛する人々が救われるように祈り、みことばを伝える必要があるのです。
二、みことばを宣べ伝えなさい 2節
パウロが命じている命令とは、「みことばを宣べ伝えなさい」と言うことです。若きテモテ、後継者への使徒の遺言は、すべての教職者、そしてすべてのキリスト者への命令です。時は厳しい、周囲には危険と患難があります。しかし、「時が良くても悪くても」しっかりとみことばを宣べ伝えなさいと言うのです。「しっかりやりなさい」エフィステーミとは、4章6節にも同じ言葉が使われおり、「近づく」「側に立つ」「そこにいる」「切迫している」等の意味を持っています。ここでは、時が良くても悪くても、「しっかりとそこに立って」みことばを宣べ伝えなさい、と言うことです。
「時が良くても」とは、「ちょうど良い時」「時宜にかなった」を意味するユーカイロスという言葉より派生しています。参照:ヘブル4章16節では、「折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか」というところに用いられています。みことばを宣べ伝えるとき、好機を得た、まさにちょうどその時と言うような追い風の時もあれば、そうでない向かい風の時もあります。
しかし、祈りつつ、伝道に励む時、主は、人々の心を動かし、状況を変えて、伝道のチャンスを与えて下さいます。
そして、「寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また勧めなさい」と言うのです。「責め」とは罪を認めさせることです。みことばの真理を示し、自らは神の御前に罪人であることを覚えさせ、キリストの十字架による救いを必要とする者であることを悟らせることです。「戒め」とは叱ることです。ガミガミ叱ることではありません。これもみことばの真理を示し、その人を目覚めさせ、キリストの福音を求める心を起させることです。「勧める」とは、励まし慰めることです。「寛容(マクロスミア)を尽くし」とは、心を最大限に広く大きく持つということです。伝道するとは、常に広い心で、あきらめることなく、絶えず教え、みことばを語って、罪を認めさせ、叱ったり、慰めたりして、一人の人のたましいを取り扱って、主に結びつける働きです。
マルコの福音書4章26~29節。みことばの種をコツコツと蒔く働きを続けてまいりましょう。
三、自分の務めを十分に果たしなさい 5節
5せつをご覧ください。「けれども、あなたはどんな場合にも慎んで、苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい」とあります。どのような時代、どのような状況になっても、慎みと忍耐をもって、伝道者としての働き、務めを十分に全うするようにというのです。
時は厳しく、困難はあっても、受け入れるものが少なくても、純粋な福音でなければ人は救われません。どのような状況にもかかわらず、私たちは、純粋な福音、真理のみことばを正しく伝える使命に励みたいものです。また、そのような宣教の働きに従事している伝道者や宣教師の先生方のために、主の助けを頂いて、その務めを十分に果たすことが出来るように、祈らなければなりません。
ああ皆さん。あなたにも、あなたでなければ福音を伝えることの出来ない人がいるのですよ。ああ!どうぞ時を逸することのないようにしていただきたい。
(結論)テモテの手紙第二4章2節の文語訳には「なんじ御言を宣べ伝えよ、機(おり)を得るも機(おり)を得ざるも常に励め」とあります。
時を失うことなく、みことばを宣べ伝えることに励んでまいりましょう。